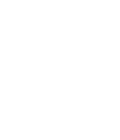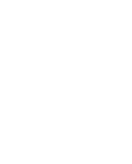子供にとっての勉強の必要性。勉強が不要な場面は意外と多い

机に向かっている時だけが勉強という解釈が大きな間違い

今回の記事のタイトル「子供にとっての勉強の必要性。勉強が不要な場面は意外と多い」となっていますが、そもそも「勉強とは」という時点で、多くの親が解釈を間違っています。
特に机に向かっている子供の姿を見て、安心する親御さんは、勉強に対して視野の狭い意識を持っているかもしれません。
勉強とは、ある一つのジャンルについて、傾倒し、精を出し、努力し、理解を深め、一人の人間として心や頭や体を強化し、人生をより豊かにしていくことです。
一つのジャンルが、学校の机の上で受ける勉強でなければならないということはないのです。
つまり、本来の勉強とは?
step1、夢中、熱中できること(集中)
step2、精を出すこと(努力)
step2、理解を深めようとすること(思考)
step3、成長すること(進化)
step4、人生を豊かにすること(幸福)
step5、周囲を幸せにすること(影響)
夢中、熱中という土台が集中力を作ります。集中力があれば、努力を出し切ることができ、非効率で不誠実な努力に対して、理解を深めようとします。理解が深まれば、そのジャンルで成長を遂げることができ、進化した心と頭と体で世界をより自分の描いた道に運ぶことができます。結果、幸福を感じられ、自分の力で、自分だけでなく、関わる人たちに幸福感を与えることができます。
親は子供の将来を考えて、勉強の大切さを説く

大人からすれば、まったくもって正しいことです。自分の経験則を踏まえたうえで、子供に勉強の大切さを説く。
ただし、子供に響くか響かないかは別です。
さらに言えば、将来を考えて、親目線の勉強論を説いてしまうことで、より勉強から遠ざかるかもしれません。
勉強の定義は国語辞典で調べると、
1.《名・ス他自》無理にでも(=強)努力して励むこと。
2.仕事に精を出すこと。
というまったく親目線、大人目線の定義が詰まっています。
子供の頃に大事なのは、夢中、熱中という土台を育むことです。
さらに言えば、「1つのジャンルに夢中になり、精を出し、理解を深め、成長し、幸福感を感じ、周りにも影響を与える」という流れを何度も経験することが大切です。
そうなれば、子供は将来的に、自分の置かれた環境から、夢中になれるものを探せるようになります。
つまり、どの環境に置かれても、集中力でスタートダッシュに成功し、きちんと努力し、成長し、幸福を勝ち取るのです。周りに影響を与えられるような存在になれば、それだけ付加価値が高まりますので、給料や社会的評価も追従してくるでしょう。
だからこそ、親は、子供の今と未来の心と頭を両方育てる視点で、勉強を考えることが、一番ベストなのです。
子供にとって、勉強(座学)が不必要な9つのケース

座学としての勉強は、学校や塾を通じて、国語、数学、英語、理科、社会のジャンルについて、子供に定期的な学びを与えてくれます。
子供にとって、このような勉強が不要なケースは、座学を超えた経験をできる状況にある場合と言えます。
よって、子供にとって、勉強(座学)が不必要なケースは…
1、子供が他の習い事に夢中である
2、子供が遊ぶことに夢中である
3、子供が勉強嫌いなのに定期テストで60点~70点は取る
4、子供が勉強以外の得意ジャンルを持っている
5、子供が本ばかりを読んでいる
6、宿題は嫌いだが授業は楽しんでいる
7、子供が多くの人に会える環境にある
8、外に出かけることが好きである
9、親がコミュニケーションを通じて常に考えさせている
といったような状況と言えるでしょう。
1、子供が他の習い事に夢中である
その習い事が何よりもの勉強です。興味を持って、1つのジャンルに深掘りして、なおかつそれに夢中になっている。まさに、子供の今と未来を輝かせる勉強です。
2、子供が遊ぶことに夢中である
一人で行う電子的なゲームから、友達とアウトドアを思いっきり駆け巡る遊びまで、すべてが勉強の要素を含んでいます。
子供は子供ならではの工夫を凝らし、考えながら、ゲームに没頭します。
親子でコミュニケーションをきちんと取れていれば、そのゲームを消費に留めずに、より考えて、成長するために熱中するジャンルに変えることができます。
ゲームと勉強との関係性については、「遊びとゲームと学びは同じベクトル」で徹底解説しておりますので、そちらもご参考に下さい。
3、子供が勉強嫌いなのに定期テストで60点~70点は取る
勉強が嫌で家で勉強をしているように見えない。でも、テストは毎回、60~70点を取る。こういった子供は、自分でスイッチを入れることができれば、すぐに良い成績を取ることができるでしょう。
自分の自然な吸収力だけで、60点~70点を取れたことを、むしろ、評価してあげて下さい。
4、子供が勉強以外の得意ジャンルを持っている
子供が自覚して得意ジャンルを持っているということは、自尊心を高め、すくすく育つ1つの大事な要素になります。
その得意ジャンルを伸ばしてあげた方が良いでしょう。
子供のペースに合った努力と、子供が自ら思考を促せる環境を親が用意することができれば、子供の頭脳はそのジャンルを通して養われていきます。もちろん、スポーツでも構いません。親のコミュニケーション能力次第では、子供が自発的にストイックに思慮深く取り組む、プロへの階段を駆け上がっていくかもしれません。
5、子供が本ばかりを読んでいる
読書はもっともベーシックな勉強と言えるでしょう。小説やハウツー本でなく、漫画だったしても、1冊の本に向き合い、イメージし、自分なりに吸収していくわけですから、かなりの読解力が身に付きます。読者は、すべての受験科目における解答力を磨くことにも繋がります。
とにかく、本を読むことが好き。そんな子供がさらに本が大好きになれるような本をチョイスしたり、本屋に行って一緒に本を見ながら、コミュニケーションを図ると、本を通じた子供の勉強を促すことができるはずです。
6、宿題は嫌いだが授業は楽しんでいる
本質的には勉強が嫌いではないと言えます。塾や家庭教師との学習であれば、実は好きなのかもしれません。子供の授業に対する状況を、世間話の中から聞き出してみましょう。「勉強=本当はやりたいこと」になっているかもしれません。また、家庭の学習環境によって、宿題のモチベーションが落ちている場合もあります。家庭学習の環境をリフレッシュさせてみましょう。
7、子供が多くの人に会える環境にある
百聞は一見に如かずと言いますが、文献に対する情報に対する情報の吸収力がまだまだ大きくなっていない子供の段階では、多くの人と会えることが何よりものインパクトのある勉強になります。また、いろんな人と会うことで、コミュニケーション発達します。子供が多くの人に会うことを拒まないのであれば、人を通した学習を促してみましょう。
8、外に出かけることが好きである
出かけるのが好きということは、興味が外へ向いているということの証です。いろんなところに出掛けながら、親が上手く知識を補足したり、質問を問いかけることによって、子供はイベントのように楽しく過ごしながらも、頭を使い、インプットとアウトプットをしていくことになります。
9、親がコミュニケーションを通じて常に考えさせている
学校での勉強は、ほとんどの場合、先生とのコミュニケーションによって成り立ちます。
先生の指導の下に、教科書やノートが勉強の道具となり、子供から質問をするというコミュニケーションによって、さらに理解を深めていきます。
だからこそ、普段から親がコミュニケーションを通じて、子供に考える時間を与えていれば、それだけで勉強になるのです。
なぞなぞでも、テレビの感想でも、ゲームのプレゼンでもなんでも構いません。子供が楽しく考えて答える。親との会話でこれができれば、座学としての勉強を強制しなくても良いのです。
子供にとって勉強(座学)が必要な3つのケース

一方で、学校の勉強を通じて、人生が変わる子供もたくさんいます。
勉強の押し付けはダメだからと言って、放任し過ぎると、実は勉強をしたいのに、勉強について親からバックアップが得られないということも起こってきます。
子供にとって、勉強(座学)が必要な場合ケースは
1、興味のあることが何もない
2、自分に自信がない
3、分からない自分に危機感を抱いている
といった状況です。なぜなら、学校の勉強は、対策を取れば、きちんとした結果が得られる一番簡単なジャンルの1つだからです。
この点がスポーツや音楽とははっきりと違います。
1、興味のあることが何もない
子供が何にも興味が湧かない。まずは粘り強く興味を探してあげることが大事ですが、学校の勉強を通じて、「学ぶ、解く、結果を出す」という訓練を磨くことも大切です。
学校の勉強を通じて、「学ぶ、解く、結果を出す」の行動体質が身についていれば、本当にやりたいことが見つかったときに、きちんと走り出すことができます。
2、自分に自信がない
自分に自信がないという子供で、学校の成績がそこまで良くないのであれば、勉強を通じた成功体験で、自信を持てるきっかけを作ることも可能です。親が強引に応援団長として一時期だけ子供をリードするのか、子供が自発的に学びたくなるような環境を作った上で、走り出すのか見極めが必要になります。テストで過去の自分との大きな変化が結果として表れ、順位で他の人よりも上になっているという経験を一つでも積むことができれば、勉強を踏み出しに、子供が自分を信じることができる人間へ成長することができます。
3、分からない自分に危機感を抱いている
危機感というのは、大きな行動力のきっかけの一つと言われています。勉強がしたくないということよりも、分からないということに危機感を覚え、どうにしかしたいと思っている。
そんな子供に、親は「気にすることない」と根拠のない励ましを贈るよりも、「どうにかしたい」に応えるカタチを贈ってあげるようにしましょう。
分からないところを聞いて、自分で教えるのも良いでしょうし、塾や添削指導などの学校外学習を選ばせるのも良いでしょう。
危機感で煽られて、どうにかしたいわけですから、どうにかしてあげましょう。こういった子供は、一旦分かれば、学ぶことの楽しさを他の子供よりも感じることができるようになります。
一瞬、一瞬が学びの本質に沿っていれば、かしこまって机に座り学ぶ必要はない

今回は子供にとっての勉強の必要性についてお話ししてきました。タイトルにある「勉強が不要な場面は意外と多い」という表現は、必ずしも、机に向かって、「これは勉強だ」と意識して、取り組む必要はないといった意味です。
子供の行動の一つ、一つに学びの本質が備わっていれば、机に向かって得られる以上のものを、日常的に吸収することができます。
・机に向かう=勉強
・机にいない時=勉強していない
こういった考えの親御さんには、現在の学校教育のしくみを構想した教育学者ヤン・アーモス・コメンスキーの言葉を贈ります。
賢くなろうとして本や黒板に教えを乞うてはならない。 天と地と林と木の葉とは、本当に子供らを賢くするであろう。
勉強は座学だけはありません。そして、学んできたことの内容も大切ですが、
学生時代に大事なのは、何を学んだかではなくて、どうやって学んだかということ。
日本のドラマ『白線流し』、登場人物の相澤先生の言葉です。ぜひ、勉強について今一度、深く考えてみて下さい。
本サイト「家庭の教育」では、家庭教育、家庭学習における大切なノウハウをまとめています。1日では閲覧し切れない内容になっていますので、ぜひ、定期的にご覧頂き、子供の勉強に活かして下さい。