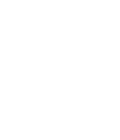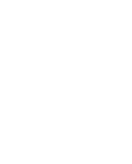机に向かう以外の家庭学習を

机に向かう以外の多彩なアプローチで子供が自然に学べる環境を

机に座って、学校の教科書、塾のテキストと対峙する。
子供の勉強をイメージすると、そこには必ず、机に向かっている子供の姿があるのではないでしょうか?
しかし、勉強とは机に向かうことだけではありません。
良い家庭学習の家庭は、学習の方法に多様性があります。
親と子供が会話をする。親が子供との会話を大事にすれば、その何気ない会話から、子供を学ばせることができます。しかも、子供は勉強と思わずに…
親が机に向かう事のみを勉強と考えると、子供の可能性は小さくなります。
「学校で勉強したことは社会では役に立たない」の本質

学校で子供たちが行っている勉強は、あくまでも勉強の1ジャンルに過ぎません。
実際に社会に出ると、机に向かって学ぶだけじゃ網羅できない知識・技術・感覚がたくさんあります。
だからこそ、「学校で勉強したことは社会で役に立たない」というギャップを多くの子供が将来的に感じるわけです。
でも、厳密に言えば、学校の勉強も、その他の勉強も、本質的には変わりません。
まず、親御さんは次の言葉を贈りたいと思います。
勉強とは、1つのジャンルを掘り下げること。
この本質を親と子供が理解しておくと、勉強に対するハードルはどんな事に対してもぐっと下がります。
スポーツと勉強の共通点を見出し、文武両道な子供にもなります。やりたいことが見つかったら、一気に努力を注ぎ込み、結果を引き寄せられるようになります。
机に向かう座学とは、いわば、
一問一答のワンパターン競技に強くなること
です。その意味では、「Qに対するA」をひたすら覚えなければいけない場面では、勉強を問わずに、力を発揮することになります。
遊びは純粋に好奇心を掘り下げる勉強

子供が遊ぶのはとても良いことです。
遊びを見つけたということは、知的好奇心をくすぐる対象に出会えたということ。
こんなにめでたいことはありません。
遊びは知的好奇心をくすぐる。
知的好奇心とは、知りたいという思い。
学びへのポジティブな姿勢。
学びのモチベーション。
遊びを通して、「1つのジャンルを掘り下げること」を徹底した方が、勉強よりもどんどん深く掘り下げて、知を吸収し、それが血となり、肉となるケースは多いのです。
だから、遊びに対して、親が質問したり、応援したり、複雑にしたり、快適にすることで、子供は遊びから自然に学んで、「学校の勉強」にきちんとフィードバックします。ちゃんと遊んで、学校の点も良い子供になります。
一度「マニア」になることを知れば、どんなフィールドでもプロになれる

「プロ」が付く仕事をしている人は、言い換えれば、全員ただの「マニア」です。
仕事のレールやルールに沿って、マニアになっているのです。
どうすれば、マニアになれるのか?それは、「1つのジャンルを掘り下げることの徹底」です。もっと、正確に言うと、「考えながらの徹底」です。考えながら徹底すれば、どんどんと狙って目標を達成できるようになります。
単なる「オタク」として否定する傾向から離れよう
「アニメやゲームに熱中するオタク」と「勉強に熱心な子供」をまったく別に捉えていませんか?どちらも「1つのジャンルを掘り下げること」を徹底している素晴らしい存在です。
でも、両者を親が分断し、一方を否定すると、子供は遊びで「1つのジャンルを掘り下げること」と、勉強のそれを分断して考えるようになります。
すると、オタクで物覚えもいいはずなのに、勉強ができない子供が生まれます。親が子供の持っているはずの才能を奪ってしまうことになるんです
親が「意味がない」と思う時間は、子供の心の回復食

子供の様々な行動に対して、大人から見たら「意味がない」と思うことは多々あるでしょう。親御さんは、どうしても、反射的には「親として」「大人として」子供の物事を捉えてしまいます。
もしも、子供が熱を入れていることに対して「意味がない」と感じたら、親という目線から一歩引いて物事を捉え直してみて下さい。
そして、子供が熱中しているその家庭をきちんと褒めてあげましょう。
親が「意味がない」と否定せずに、子供が思う存分に行動を取ることで、掘り下げる癖だけでなく、その行動がポジティブな「心の拠り所」になります。切り替えて、勉強も自発的に行えるようになるでしょう。
一方、親の否定が強すぎると、ネガティブを忘れるための「心の拠り所」になり、心の依存先へとなってしまいます。
すべての行動は「考えれば」勉強へと昇華できる

子供が今いる場所に考えを巡らせれば、目の前の景色は学びを得られるコンテンツになります。子供が考えようと自発的になれば、
計画を練る/企画を立てる/誰かに教える/基準を覚える/ルールを決める/ルールの中で工夫する/想像を膨らませる/アイデアを提案する/物語を作る/物語を読み取る/公式を覚える/公式を掴む
という行動が、普段からできるわけです。「いざ、勉強」と構えなくても、もしかしたら、まったく机に向かわなくても、将来は机に向かった人間よりも、結果の出せる大人になっていくでしょう。
だから、「勉強の意義」を唱えて、机に向かわせるよりも、「考える楽しさ」をコミュニケーションを通じて体験させ、知の喜びを与えた方が、数百倍子供の人生はキラキラするのです。
子供が机に向かうことを「退屈」と思わせないように

そもそも机に向かうことがなぜ、嫌になるのか?それは、勉強に強い義務感が働くから。さらには、勉強よりもやりたいことがあり、その「妨げ」になるから。
極めつけは、親が義務感と束縛感のある勉強への強制を煽るから。
勉強は「強制」ではなく「共生」を促しましょう。淡々と日々両立できる子供いますし、日ごとにオンとオフをはっきりさせたり、数週間・数か月と期間ごとに1点集中するジャンルを変えたり、子供によって、最適な勉強との「共生」の仕方は様々です。
子供の人生は自分で考えて選んでこそ、確かな道が開けます。
子供の勉強に対する「共生」を自ら思考し、計画し、実行し、反省し、工夫できるように、親としてバックアップしていきましょう。